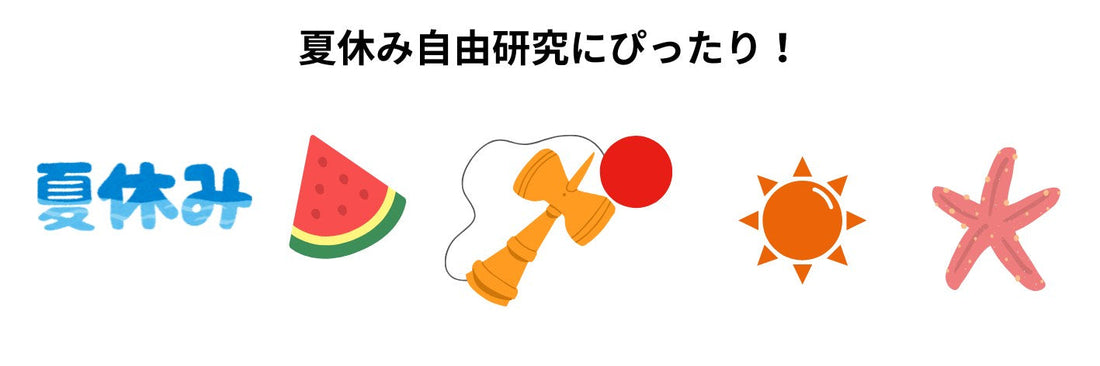
夏休み自由研究にぴったり!けん玉の歴史から実験・体験までアイディアを完全ガイド
共有
いよいよ学生の皆さんお待ちかねの夏休みですね!
今回は夏休みの自由研究、何にしようか迷っているみなさんへご提案です。
伝統的なおもちゃ「けん玉」を題材に、自分だけのオリジナル研究に挑戦してみませんか?
遊んで楽しいだけでなく、歴史や文化を学べて、実験・体験記も作成しやすいのが魅力です。
1.けん玉の歴史をひもとこう
けん玉は大正時代(1912年〜1926年)、1918年に江草濱次氏が「日月ボール」(にちげつボール)を考案し、玉を皿で受けるという今の形を確立したと言われていいます。
元は江戸時代の庶民の遊びとして広まり、明治~昭和には子どもたちの必須アイテムに。
戦後は一時ブームが冷めましたが、昭和50年(1975年)、日本けん玉協会が設立。
統一規格、共通ルールが整備され、スポーツや競技として確立しました。
現在では世界中で愛好者がいる、国際的な伝統玩具です。
2. けん玉の“いま”──国内外で広がる文化
- 国内:学校の課外活動や市民イベントで「けん玉教室」が多数開催
- 海外:アメリカ・ヨーロッパを中心に「Kendama USA」「KROM」などの各国でブランドが展開
- YouTubeやInstagramでは、プロプレイヤーによるハウツー動画やトリック動画が大人気
3. 自由研究のアイデア
-
歴史調査:参考書籍やウェブサイトを使って、日本での誕生~現代までの流れをまとめる。
-
文化比較:日本・アメリカ・ヨーロッパでのけん玉人気事情を調べ、写真やデータで比較。(例:YouTubeの登録者数、イベント数)
-
実験:同じ技(例えば、ふりけんや飛行機なそ)でも、けん玉の材質(かえで/さくら/ぶな等)や、塗装の種類(マット、スティッキー、無塗装など)で成功率がどう変わるか実験。
ポイント:成功率を記録して表やグラフにまとめよう。
-
体験記:実際にトリック(飛行機/大皿周りなど)に挑戦し、成長の様子を写真付きで記録。
-
まとめ:研究結果を振り返り、自由研究の感想と今後の目標を書く。
4. 研究におすすめのけん玉3選
-
山形工房 大空シリーズ(無塗装、マット、クリアなど)
日本けん玉協会認定の製品で、扱いやすく日本製のけん玉の代表選手
-
TOKYO KENDAMA 5thシリーズ(無塗装)
様々な木材で作られた商品が魅力。「育てるけん玉」をテーマにしています。5thシェイプは大きなカップでキャッチしやすく、自由研究の実験にぴったり。
-
KROM POP(スティッキー、ラバーなど)
カラフルで玉のコーティングもグリップが効いて技も決めやすい。入門の1本にピッタリ!
5. まとめ:自分だけのオリジナル研究を完成させよう!
けん玉は「遊び」「学び」「実験」がぎゅっとつまった自由研究にうってつけのテーマです。
歴史や文化を学んでから、実際に手を動かして実験し、最後にレポート&プレゼンをすれば、大人もうなるクオリティに!
夏休みの自由研究、今年はぜひ「けん玉」にチャレンジしてみてはいかがでしょう?
